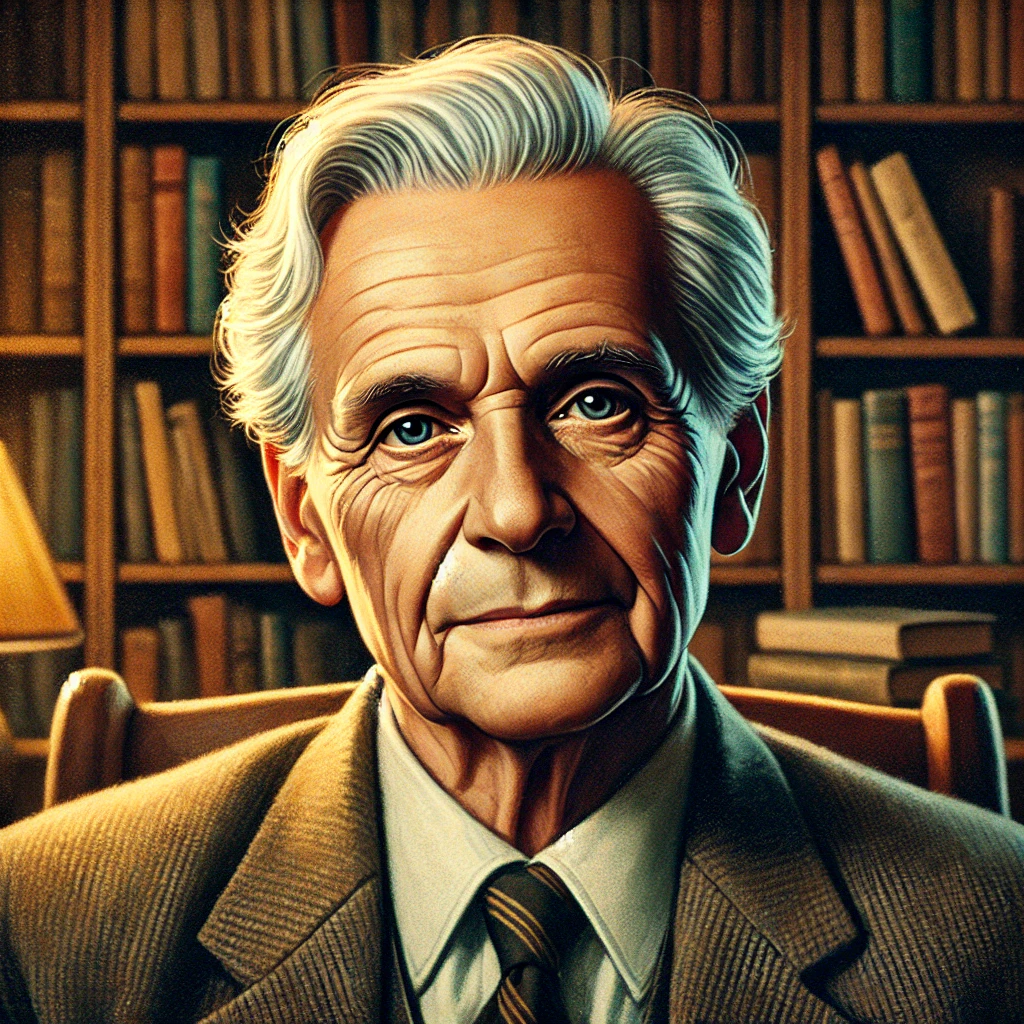1 寛容のパラドクスの概要
『寛容のパラドクス』とは、次のような論理構造で説明される。すなわち、
①寛容な社会というのは、ある個人の主張について、寛容な(受け入れ、許す)社会をいう。
②個人の中には、他者の意見に対して寛容な立場を示す者もいれば、他者の意見に対して不寛容な立場(認めない、受け入れない立場)を示す者もいる。
③それならば、寛容な社会というのは、不寛容な立場の者に対しても寛容な(他者の意見を許さないような者をも許す)社会であるのが論理的帰結である。
④他者の意見に対して不寛容な者は、他者の意見を批判し、攻撃し、排斥する。その批判・攻撃・排斥が一定程度続くと、その者とは違った意見を持っている者は淘汰されていく。
⑤やがて、他者の意見に対する不寛容さが力をもった社会が完成する。すなわち、当初社会が目指した寛容さは、奪われ、破壊され、もはや残らなくなってしまうのである。
①〜⑤をまとめると、寛容な社会というものが他者に対して不寛容な立場を許す社会なのであれば、やがて不寛容な社会が生まれるだろうということだ。
寛容な社会の帰結が不寛容な社会である点に矛盾が生じているため、『寛容のパラドクス』と呼ばれている。
2 問題となる具体的場面
例えば、人種に関するヘイトスピーチを行う人たちが特定の人種の者が日本に存在することを許さない旨の主張を繰り広げるとする。
この立場は、特定の人種の者の存在を許さないという点で不寛容な立場だ。
ヘイトスピーチを行う人たちが、このような主張も「言論の自由の一種だ」「だから、許容されるべきだ」と主張することが考えられる。
言論の自由を無制限に認めるような寛容な社会であれば、ヘイトスピーチを行う人たちの言論の自由も確保すべきということになりうる。
ヘイトスピーチを行う人たちの主張が通る社会は、寛容をうたってはいるが、結局のところ、激しい攻撃を受ける特定の人種の者を護ることができない。言い換えれば、その人種の者に対しては、不寛容な社会にほかならない。
この具体例では、寛容をうたった社会なのに、特定の人種の者に対しては寛容とは言い難い結果を生じさせている。そのため、社会に矛盾を発生させてしまっている。
3 寛容な社会を維持するためには?
(1) カール・ポパーの立場
この『寛容のパラドクス』を語る上で、避けては通れないのが、カール・ポパーだ。
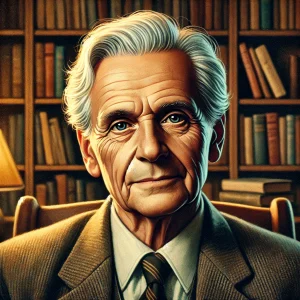
カール・ポパー(ChatGPTが作成してくれました)
彼は、寛容な社会を維持するための方法について、次のように述べている。
寛容な社会を維持するためには、寛容な社会は不寛容に不寛容であらねばならない。
(2) カール・ポパーの立場の考察
先ほど確認したとおり、寛容をうたった社会が、もし他者に対して攻撃するような不寛容な立場を擁護するのであれば、その結末は、不寛容を許す社会、すなわち、不寛容な社会となる。
寛容さを大切にしすぎるがあまり、他者を攻撃するような不寛容な立場を擁護し、その攻撃を受ける者たちを保護しないのであれば、寛容さは社会から消えてしまう。
結局のところ、他者に対して不寛容な者を制限して、その脅威にさらされる者を護る覚悟ができていないのであれば(そこで最初に示した③の論理的帰結を曲げられないのであれば)、寛容な社会など、実現することは不可能なのだ。
だからこそ、寛容な社会を真に実現したいのであれば、不寛容な立場の者を許してはならない。不寛容な立場の者から、排斥される者を身を挺して護る必要があるのだ。
カール・ポパーの言説の趣旨は、以上のようなものではないかと思う。
このカール・ポパーの立場も、先に指摘した矛盾を解消したものとは言い難い。なぜならば、
寛容な社会をうたいながら、他者に対して不寛容な者に対して、一定の制限を与えるのであれば、不寛容な者に対して、寛容な立場をとってはいないことを意味するからである。
しかし、このカール・ポパーの立場をとれば、寛容をうたう社会は、その不寛容を除きさえすれば、寛容な社会として維持されるだろう。
この意味では、当初の『寛容のパラドクス』をある意味打ち破ったものといえ、1つの真理といえよう。
(3) 不寛容な立場への不寛容はいつ発動すべきなのか?①──問題提起
それでは、不寛容な者による他者への攻撃がどの段階に至った場合に、その立場の者を制限すれば良いのだろうか。
他者に対して不寛容な者がいるとしても、ただ批判をしただけで排斥すべきだとすれば、言論の自由などなかったも同然だ。
しかし、その攻撃の程度が一定程度を超えた場合には、制限を加えなければ、寛容な社会を護ることはできない。
その「一定程度」というのは、具体的には、どの程度をいうのか。それがここで取り上げたい問題だ。
(4) 不寛容な立場への不寛容はいつ発動すべきなのか?②──1つの考え方
先ほどの問いに対する答えを用意するとすれば、「言論によって対応することができる範囲を超えたとき」というのがありうる。

様々な人が話しあいで解決しようとしている場面のイメージ(ChatGPTが作成してくれました。)
何らかの批判を受けた者が、その批判に対して、言論で対抗することができるのであれば、その言論での対抗に任せておけば良い。これはまさに言論の自由が正しく機能している場面といえる。
もし、何らかの批判を受けた者が、その批判に対して、返答する価値もないと考えるのであれば、その場合もあえて介入する必要はなく、放置しておいても良いかもしれない。
しかし、何らかの批判が実力行使を伴うようなものである場合は別である。実力行使を言論で抵抗することは困難だからだ。
何らかの批判が人格攻撃に及ぶようなものである場合も別である。人格攻撃はもはや言論で対抗したところで何も被害が回復されない性質のものだからだ。
4 寛容な社会をつくるための提言
提言などできる大した立場を持ち合わせているわけではない。が、
寛容な社会──私なりに言い換えれば、誰もが一定以上は幸せに暮らすことができる社会──をつくるためには、「言論によって対抗が困難なもの」を見た場合には、なんらかのアクションをとっても良いのではないか。
何のアクションもとらず、目の前の不寛容を見過ごしたとき、次に不寛容の脅威にさらされるのは、あなたかもしれない。